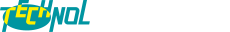- HOME
- 法令について
法令について
測定について (関係法令の条文等は該当部分のみ抜粋して掲載しております。)
各種法令で放射線業務従事者等の個人放射線被ばく線量の測定および記録(保管)が義務付けられています。
労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
1測定の義務
(線量の測定)
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うものとする。
6 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者は、第三項ただし書の場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。
2線量計の装着位置
(線量の測定)
第八条
3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
- 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
- 二 頭・
頸 部、胸・上腕部及び腹・大腿 部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿 部である場合を除く。) - 三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・
頸 部、胸・上腕部及び腹・大腿 部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)
3線量限度
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
- 一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
- 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
4線量の測定結果保管の義務
(線量の測定結果の確認、記録等)
第九条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
- 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(次号又は第三号に掲げるものを除く。)の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計
- 二 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次号に掲げるものを除く。)の実効線量の三月ごと及び一年ごとの合計
- 三 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(緊急作業に従事するものに限る。)の実効線量の一月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計
- 四 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、三月ごと及び一年ごとの合計)
- 五 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計)
- 六 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計
3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、放射線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。
医療法施行規則
1測定の義務
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十八 病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
2線量計の装着位置
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十八
2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
- 一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
- 二 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
- 三 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
3線量限度
(線量限度)
第三十条の二十七 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
- 一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
- 二 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
- 三 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
- 四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
2 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
- 一 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
- 二 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
- 三 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
4線量の測定結果保管の義務
記載なし
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(一部抜粋)
1測定の義務
(測定)
第二十条 法第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
- 一 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
- 二 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
2線量計の装着位置
(測定)
第二十条
2 法第二十条第二項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
- 一 外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
- イ 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
- ロ 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イによる測定に加え、当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
- ハ 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、イ又はロによる測定に加え、当該部位について、七十マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
- ニ 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、イからハまでの測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
- ホ 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこれらの値を算出することとする。
- ヘ 管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
3線量限度
(用語の定義)
第一条
- 十 実効線量限度 放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
- 十一 等価線量限度 放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
→放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
4線量の測定結果保管の義務
(測定)
第二十条 法第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
4 法第二十条第三項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
- 一 第一項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、五年間これを保存すること。
- イ 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
- ロ 測定箇所
- ハ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
- ニ 放射線測定器の種類及び型式
- ホ 測定方法
- ヘ 測定結果
- 二 外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
- イ 測定対象者の氏名
- ロ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
- ハ 放射線測定器の種類及び型式
- ニ 測定方法
- ホ 測定部位及び測定結果
- 五 第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
- イ 算定年月日
- ロ 対象者の氏名
- ハ 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
- ニ 算定対象期間
- ホ 実効線量
- ヘ 等価線量及び組織名
- 五のニ 前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
- イ 集計年月日
- ロ 対象者の氏名
- ハ 集計した者の氏名(集計した者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
- ニ 集計対象期間
- ホ 累積実効線量
- 五の三 前号の規定は、第五号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
- 六 当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録の都度交付すること。
- 七 第二号から第五号の三までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
- 八 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
5放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
最終改正 令和二年十二月十七日 原子力規制委員会告示第十三号
(実効線量限度)
第五条 規則第一条第十号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における線量限度は,次のとおりとする。
- 一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
- 二 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
- 三 女子(妊娠不能と診断された者,妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については,前二号に規定するほか,四月一日,七月一日,十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
- 四 妊娠中である女子については,第一号及び第二号に規定するほか,本人の申出等により許可届出使用者
又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知つたときから出産までの間につき,人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について一ミリシーベルト
(等価線量限度)
第六条 規則第一条第十一号に規定する放射線業務従事者の各組織の一定期間内における線量限度は,次のとおりとする。
- 一 眼の水晶体については,四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト及び平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
- 二 皮膚については,四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト
- 三 妊娠中である女子の腹部表面については,前条第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
線量限度超過時の対応 (関係法令の条文等は該当部分のみ抜粋して掲載しております。)
各種法令で個人放射線被ばく線量が法令で定められたを限度を超過した場合に、該当者への診察・処置や監督官庁への報告が義務付けられています。
労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
1健康診断
(診察等)
第四十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
- 二 第四条第一項又は第五条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
- 三 放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者
2監督官庁への報告
(診察等)
第四十四条
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(一部抜粋)
1健康診断
(健康診断)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
- 三 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
- 二 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
2監督官庁への報告
(事故等の報告)
第二十八条の三 法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 八 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
医療法施行規則
1健康診断
記載なし
2監督官庁への報告
記載なし
健康診断 (関係法令の条文等は該当部分のみ抜粋して掲載しております。)
各種法令で放射線業務従事者等に対する健康診断の実施と記録(保管)が義務付けられています。
労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
1健康診断の義務
(健康診断)
第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
- 二 白血球数及び白血球百分率の検査
- 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
- 四 白内障に関する眼の検査
- 五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
2健康診断の結果の保管
(健康診断の結果の記録)
第五十七条 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)にあつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十七条の二 電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
2 緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
3通知・報告など
(健康診断の結果の通知)
第五十七条の三 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。
(健康診断結果報告)
第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(健康診断等に基づく措置)
第五十九条 事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(一部抜粋)
1健康診断の義務
(健康診断)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
- 一 放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
- 二 前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。
- 三 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
- イ 放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
- ロ 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
- ハ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
- ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
- 四 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
- 五 問診は、次の事項について行うこと。
- イ 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ及び第二十三条第一号において同じ。)の被ばく歴の有無
- ロ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
- 六 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。
- イ 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
- ロ 皮膚
- ハ 眼
- ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2健康診断の結果の保管
(健康診断)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
2 法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一 健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。
- イ 実施年月日
- ロ 対象者の氏名
- ハ 健康診断を行つた医師名
- ニ 健康診断の結果
- ホ 健康診断の結果に基づいて講じた措置
- 三 第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
- 四 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
3通知・報告など
(健康診断の結果の通知)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
2 法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
- 二 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。
医療法施行規則
1健康診断の義務
記載なし
2健康診断の結果の保管
記載なし
3通知・報告など
記載なし
教育訓練 (関係法令の条文等は該当部分のみ抜粋して掲載しております。)
各種法令で放射線業務従事者等への教育訓練の実施が定められています。
労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
1教育の実施
(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第五十二条の五 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一 透過写真の撮影の作業の方法
- 二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
- 三 電離放射線の生体に与える影響
- 四 関係法令
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
労働安全衛生法(電離則の上位法令)では新たに業務に就く前、定期の教育訓練が義務付けられているが、具体的な項目、時間は以下のとおり定まっていない。
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(一部抜粋)
(放射線障害の防止に関する教育訓練)
第二十一条の二 法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
- 一 管理区域に立ち入る者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第五号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。
- 二 放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
- 三 取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
- 四 前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
- イ 放射線の人体に与える影響
- ロ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
- ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
- 五 前号に規定する者以外の者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第四号又は第五号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
3 前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
医療法施行規則
1教育の実施
第一条の十一
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
- 三 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
- イ 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
- 三の二 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
- イ 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
- ロ 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施